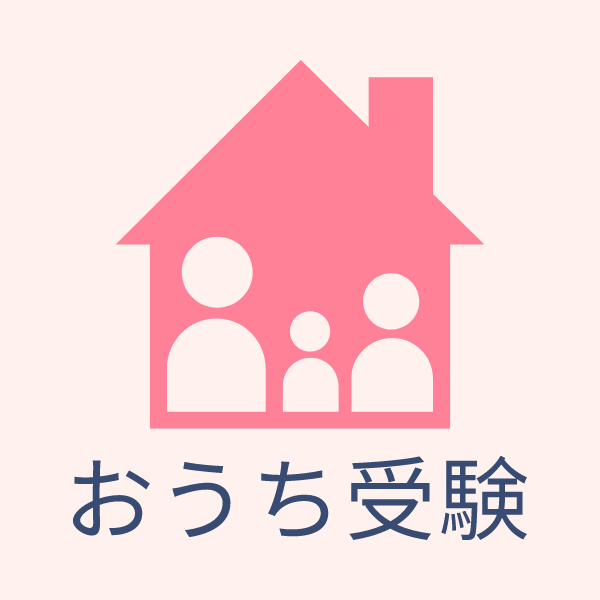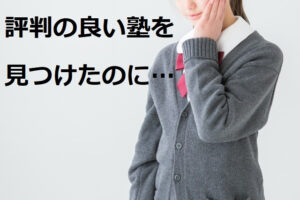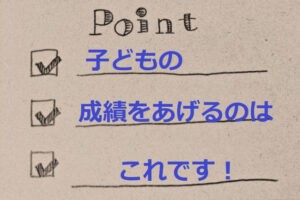成績が上がらない中学生の3つの見落とし-親が知りたい本質と対処法
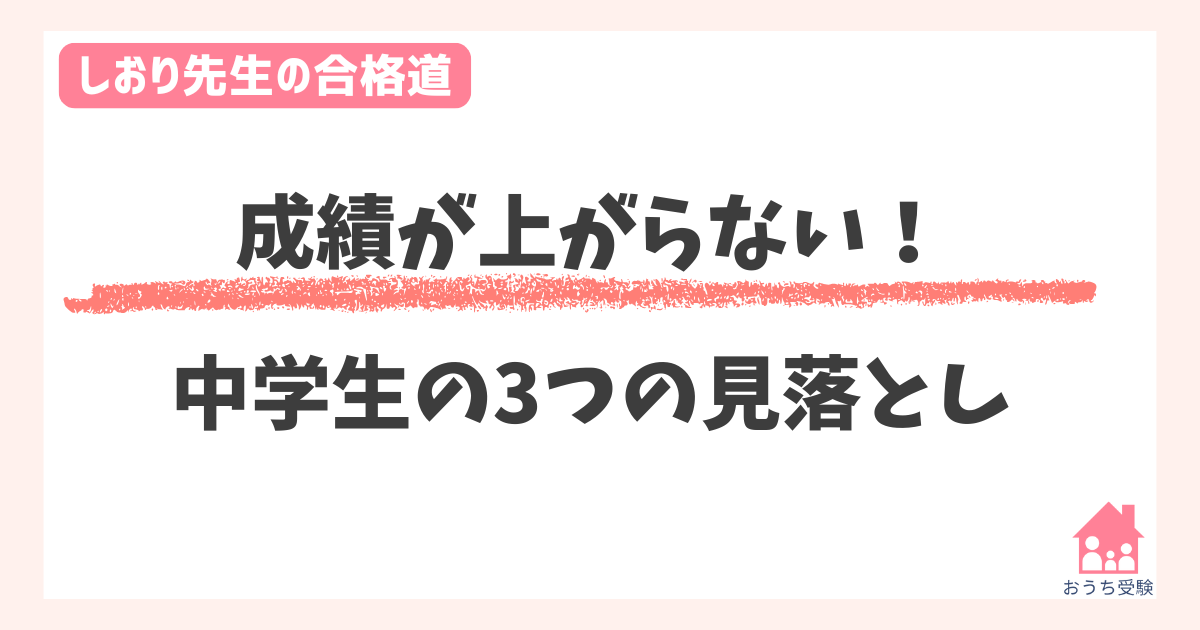
毎日机に向かっているのに…成績が上がらないのは「努力不足」ではない
「毎日ちゃんと机に向かっているのに、どうして成績が上がらないのだろう…」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。テスト前は遅くまで頑張っているのになかなか結果が出ないお子さんを見ると、心配になりますよね。
実は、成績が伸び悩む中学生には共通する「7つの原因」があります。その中でも特に厄介なのが、親も子も気づきにくい3つの見落としです。
テキストや勉強法を変えても成果が出ない背景には、「努力の方向性」「定着の仕方」「関わり方」に見えないズレがあることが多いのです。
この記事では、そうした見落としの正体を3つの視点から解説し、親が今日からできる具体的なサポート方法をお伝えします。
見落とし①:「やり方より 方向性 がズレている」
原因
テストの範囲と違う部分を一生懸命勉強していたり、自分の苦手分野を把握せず、得意な教科ばかりに時間をかけていたりするケースです。努力が点数に結びつかず、お子さんが徒労感を感じてしまいます。
対処法
- 現状分析: 定期テストの結果や模試の成績表を分析し、「どの単元で点数を落としているのか」「どこが弱点なのか」を客観的に把握します。
- 目標の明確化: 次のテストで「何点取りたいのか」「どの分野を重点的に攻略するのか」を親子で話し合い、具体的な目標を設定します。
見落とし②:復習の仕方が浅く、「わかったつもり」で終わる
原因
授業を聞いたり、解答を見ながら問題を解いたりしただけで「理解した」と錯覚してしまう状態です。自分の言葉で説明できなかったり、少し応用されただけで解けなくなったりします。
対処法
- 説明してみる: 学習した内容を、親や友人に「先生役」として説明してみることで、理解が曖昧な部分が明確になります。
- 時間を置いて解き直す: 一度解けた問題も、1日後、1週間後など、時間を空けて再度解き直してみましょう。本当に定着しているかを確認できます。
見落とし③:親のサポートが「指導に寄りすぎている」
原因
子どもを思うあまり、親が「勉強しなさい」「もっとこうしなさい」と細かく指示・管理しすぎてしまう状態です。これは子どもの自主性を奪い、「親のために勉強している」という意識にさせてしまいます。
対処法
- 「管理」から「伴走」へ: 親は監督ではなく、子どもの一番の応援団でありサポーターであるというスタンスが大切です。子どもの意見を尊重し、一緒に悩み、考える姿勢を見せましょう。
- 質問で思考を促す: 「どうしてそう考えたの?」「他に方法はありそう?」など、答えを教えるのではなく、子ども自身が考えるきっかけとなる質問を投げかけることが、思考力を育みます。
成績が伸びる子の共通点:3つの見落としを克服した先にある変化
成績が伸びる生徒は、これらの「見落とし」を克服し、以下のような好循環を生み出しています。
- メタ認知能力が高い: 自分の学習状況を客観的に把握し、「何が分かっていないのか」「どうすれば理解できるのか」を自分で考える力があります。
- 学習を習慣化できている: 「やるぞ」と意気込まなくても、歯磨きのように自然と机に向かう習慣が身についています。
- 失敗を恐れない: 間違えることを学びの機会と捉え、なぜ間違えたのかを分析し、次に活かすことができます。
親子で変わる第一歩:一緒に考えてくれる存在をつくる
「やる気がないわけじゃないのに、どうサポートすればいいか分からない」そんなときこそ、親も一緒に学べる環境が必要です。
オンラインの個別コーチングでは、専門のコーチが第三者として、
- お子さんの学習状況を客観的に分析し、
- どこに見落としがあるのかを一緒に整理し、
- 親御さんにも寄り添ったサポート方法を提案します。
親御さんが一人で悩みを抱え込まず、一緒に解決策を考えてくれる存在を持つことが、成績アップへの大きな第一歩となります。
今すぐ資料請求して、お子さんに合った学び方を見つけるサポートを始めてみませんか?
\今すぐ資料請求はこちら/